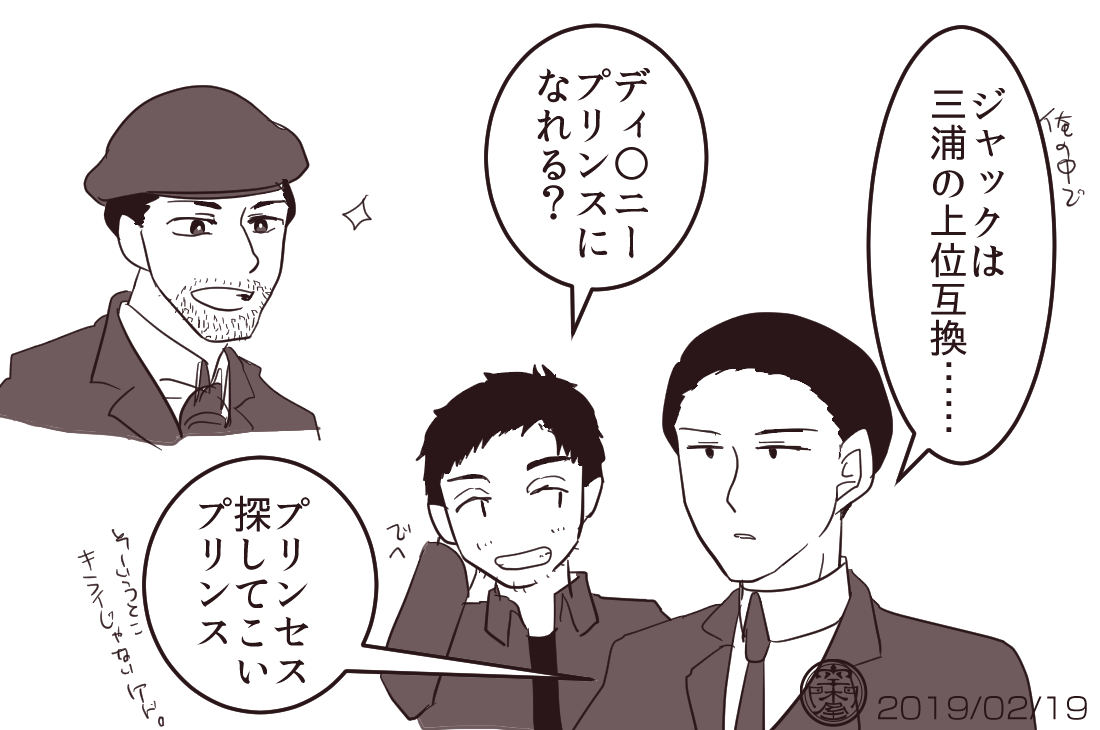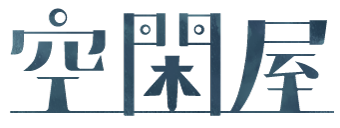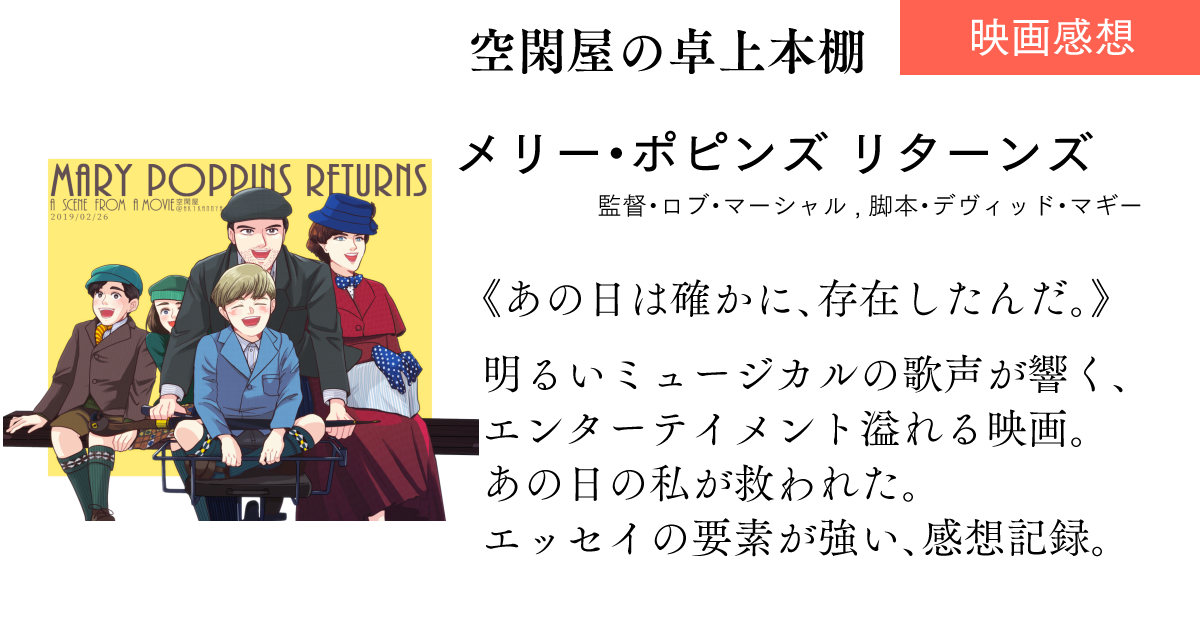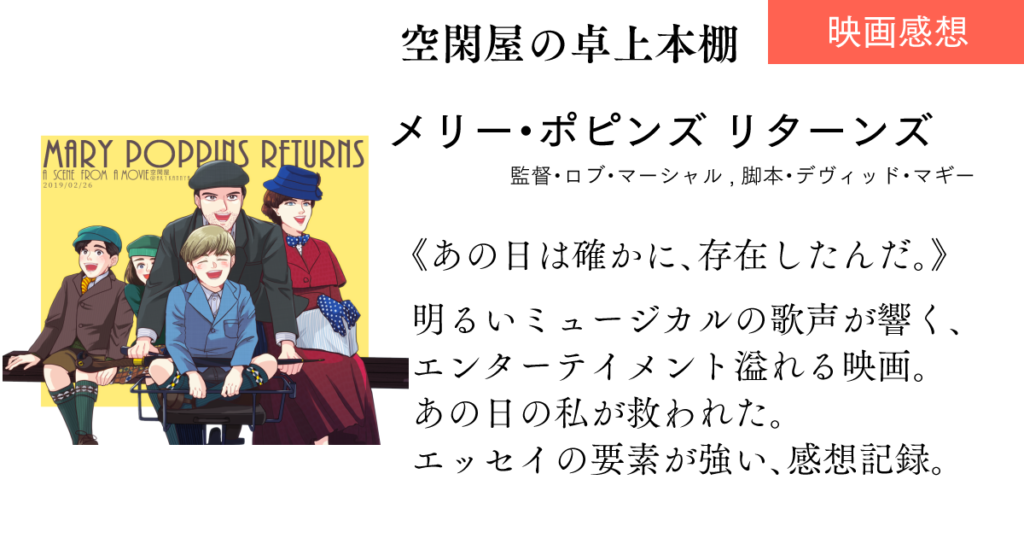
(2019年に別所で投稿したものを再掲したものとなっています。)
※ネタバレ含みます
メリーポピンズリターンズを見ました。結論から言うと私は救われて、でもきっと、この涙があふれてどうしようもない気持ちは他人に理解されないだろう、と思っています。思っているからこそ、せっかくだし文字にしようと思いました。私にとって映画感想と言うにはあまりに癒着したこれは、文字で向き合いたいものだったからです。
冷静な私の部分で感想を言うと、涙を零したとしてもその涙で呼吸が難しくなるような作品ではないと分かっています。笑って、音楽を浴びて、よかったねと終える物語だと分かっているのです。けれども私にとって、この映画はそれだけでなかった。そのひとつの事実があまりに強すぎました。
私のこのややこしい感情はあとにするとして。簡単に冷静な感想を言うなら、とても明るく素敵なミュージカルでした。
私はミュージカル映画に疎く、そもそも映画自体にも疎い人間です。時々見に行って触れる物語を楽しむだけで、いわゆる背景とかを考えるタイプではありません。リターンズ、とのことで、名前だけは聞いたことがある映画の続編なのだと理解して見ないでおこう、と最初は考えていたくらいです。お恥ずかしい話、煙突掃除の歌がメリーポピンズだったことも映画を見た後家族から聞いて知ったくらいでした。
そんな私が何故見に行ったのかというと、単純にツイッターのフォロワーさんに薦められたからです。映画の無料一回分が貯まっていたのに切れてしまう、でも見たいものが丁度ないと考えていたところ、「空代さんならメリーポピンズリターンズがいいと思うよ」とお薦めされて軽率に見に行きました。なにも考えないでめいいっぱい楽しんで、そういう時間を満喫するものだということだけ聞いて、以前予告で見たメリーポピンズが美しくて衣装も可愛らしく、いいな、と思っていたのもあってのお試し感覚でした。
物語への期待スイッチを出来るだけオフにして、ミュージカルを浴びにいったのは結論から言うと自分に丁度いい心構えでした。時々演出や言葉選びなどで好みじゃなくても「そもそもミュージカルを浴びに来たのだし」「この言葉、価値観が好ましい人たち向けの映画なのだな」と思って気にしないで好きな場所だけ拾い上げられるからです。私は少しだけ人より気にしてしまうところがあって、例えば子供の物語なら大人が子供を見ないで子供が抜け出すとか、やらなきゃ、と思うことは子供にとって冒険を許される事だけれども大人に子供を見てほしいなあと思うこととか、亡くなった人と生きている人を重ねすぎるのは怖いとか、そういうところがあるからこそスイッチをオフにするのは、仕方ない、で終えることを気にせずに出来てミュージカルを満喫できました。
好きなところは幾つもあります。家族の問題に対してメリーポピンズと言う他人が介入してくれたこと、そして更にそこに他人のジャックが入ってくれたこと。メリーポピンズとジャックに恋愛がないところなど、特に安心して見られました。私は相棒、という関係が好きで、ジャックの恋愛がメリーポピンズ以外であり、しかも濃厚ではなくあくまでエッセンス程度だったことはとても嬉しかったです。
例えばその嘘と言われるような空想を、見ない人に押し付けないところも好きでした。見ない人を責めない。可哀想、という扱いがたまにありましたが、基本的にはそのままにしてくれます。そうして空想を支援する。一緒に見て、笑って、大丈夫。子供の夢を、メリーポピンズとジャックは、見守ってくれます。そしてそんなジャックが馬鹿にされず笑われることがないことも、すごくいとしいものでした。彼は真っ直ぐ、やさしく、愛してくれる人なのだということが、他の登場人物から汚されなくて嬉しかったです。
ミュージカルは軽快で、私はあまりミュージカルに詳しくないのですが、歌を聞くのが楽しかったです。吹き替えからみたのですが、字幕も見ました。吹き替えのメリーポピンズの声の方が好きな歌を歌っていた方で安心はしていましたが、実際聞いて好きな歌声でとても心地よくて。ああ、明るくて、のびのびとした歌声で、浴びる、という言葉がしっくりきて心地よかったのを覚えています。
ジャックはパンフレットの扱いを見るに準主役に近い立ち位置なのだと思いますが、映画を見ての私の感想は、メリーポピンズと言う主人公《ヒロイン》と子供たちという準主役、ジャックはメインキャラクタでありながらそのふたつを追い越さない、ところが好き、でした。こんなこというと、どこみているのだと言われてしまうかもしれませんが。
私にとって、子供たちの冒険をサポートする優しいおじさん、がジャックでした。やっていることは非常にすごくて主人公《ヒーロー》のようなのに、あくまで普通の人で、恰好よくて大好きになるのに特別にはならない。そこが大好きで、そんなジャックが子供たちをみていることがとても嬉しくて、ああ、見てよかった、と思っていました。
映画が終わる頃。別れが風に運ばれます。私は、私は心のそういうスイッチをオフにしたから、仕方ない、と思いました。いい話だった、仕方ない。諦めと受容。私は覚悟して、その行き先をぼうっと眺めました。心を諦めにしなければ、と思いました。この幸せな物語を、悲しく思いたくなかったからです。
なんでそんなこと、と思うかもしれませんが、これは私の基準のひとつで、だからこそスイッチをオフに、と繰り返しました。私は、記憶を失う、ということがとても苦手です。物語として感動を呼び、特別を強め、好まれるこの要素を非常に恐ろしく思います。記憶を失う、別れ、思い出せない。悲しくて悲しくて苦しくて、忘れられることを思えばさみしくて、忘れてしまうことを思えばおそろしくて仕方ないくらいに、苦手な要素が、この忘却です。
それでも彼らは笑っています。ほんの少しの寂しさがあっても、過ごした時間を幸せ以外に塗りたくありませんでした。かれらの結果を受け入れたい、と思っていました。別れが来ます。そう、当たり前です。仕方ない。私は諦めていました。それでも彼らは笑っているから。あの歌声は明るくて、彼らに春が来たのだから。私はそれを嘆きたくなくて――
「忘れないよ、メリーポピンズ」
ジャックの言葉は、私にとっての扉でした。その瞬間、涙がボロボロと零れました。スタッフロールが流れる中で嗚咽を漏らさないことに必死になりながら、涙を流しました。この言葉は私にとって救いで――許しだったのです。諦めきった私に訪れた優しい許しはあまりにやわらかい声で、私は、今でもその言葉を浮かべるだけで涙を零してしまいます。この記事を書きながら、泣いています。
滑稽だ、と思われるでしょう。気味が悪いかもしれません。なんでそんなに泣いてしまうのか。これは作品のすばらしさでも作り手の意図をくみ取ったのでもない、あまりに身勝手で、しかし私が物語を書くときに読者に夢見る事でした。私は小説を書いています。そして言葉はいかに母国語を同じにしても、夕焼けの色に寂しさを抱くか暖かさを抱くか別れを思うか家を思うか違うように、言葉の色や物事の受け止め方は読者によって変わり、だからこそ物語は読んだ人の物になる、そういう考え方をしています。
だから私は製作者に申し訳ないと思いながらも、この歪んでしまった経験による気持ちを大事に大事に抱えて、今、文章を書いています。
ここからは、感想と言うよりエッセイとなります。エッセイとならざる得ないもので、苦手な方は奇妙な感想だったとしてここで終えてください。
私が何故こんなに揺れてしまったかというのを説明するには、まず、私にとって物語がなんだったのか、を語る必要があります。私は物語を愛してきました。それは文章であれ、絵であれ、映像であれ変わりありません。どれを多く好むかは自分の好みで代わりますが、物語、自体が好きでした。私が愛せないものすら、物語であることがうれしく、愛せないので不満を言っても、しかしその存在があり続けることを愛しいと思っていました。
幼少期から、本を読んでいました。文学はわかりません。小難しい理屈は述べられません。ですが文学を愛したいと思っていましたし、文字というものを、言葉を愛していました。文学は憧れで、美しく、私はずっと片思いをしてきました。片思い、でした。
私の母は、少し奇妙な人でした。別に虐待などあったわけでもなく、ごく普通に育てられたのでそういうものではありません。暴力も放棄もされていません。ただ、あの人は理系で、なんでもそれなりに出来、その中でも理系よりの姉を好んでいました。そして、国語を愛した私は、気味の悪い子供、でした。
あの人曰く、国語が出来る人間は性格が悪い、とのことでした。今は全力で否定して、全力で私を抱きしめてあげられますが、小学生の私はその言葉を否定できませんでした。私が当時の私を愛したいと思うのは、「国語、本は素敵だ。勉強だってする。だからこれは悪ではない。私がこれらの能力を高く持つことが悪なのだ」と理解したところです。私にとって国語という学問は貴ぶべきことで、しかし同時に私が追求することは罪悪になる。この奇妙な矛盾は私が国語を愛し続けるための自己防衛だったのだと思います。私は、国語を愛して、同時にその愛が悪なのだという片思いを受け止めることになりました。
九十点後半でも、かならずテストで間違えているのは漢字で、勉強していないからだ、ずるいやつだと言われました。漢字の出ないテストで百点をとったとき喜んで見せにいったら怒られたのも覚えています。馬鹿な私ですね。でも、小学生だったからしかたないかな、とも思っていて、結局そのままでした。高校で学校一番、も、国語でしょで呆れられる。そういう人であることを、当時はわかっていなかったのだと思います。
だからずっと、片思いでした。文学の勉強をしたい。文字に関わる人になりたい。小学生の時、夢見たのは編集者でした。でも、一度姉に笑い話で「むりだよね」と言っただけで、どこにも残さず、その一度きり以外は胸の中にしまって、頭が悪いから無理なんだ、と諦めていました。文学の勉強をしたいなんて、私のような頭の悪い人間が、性格が悪い人間が望むなんて罪悪だと本気で思っていて、それでも本が大好きで大好きで、小説だって自分で書いて、ひとりで楽しむくらいには大好きで仕方なかった片思いでした。
面白いことに、あの人は「本を読む子供は賢い」という見た目から読書を禁じることはありませんでした。私は本を読んでいても怒られない、という理由で学校に持ち込める娯楽としても好んでいましたし、よく読んでいました。今は全然読まなくなってしまいましたが、学生という時間は物語に向かっていました。
さて、突然ですが、本を読む理由ってなんでしょうか。私は物語を愛していました。物語はとにかくいろんなことがあって、それが楽しかったです。絵本から始まり、なんでも、そういうものがとても私の心を明るくしました。
でもそれは、本を読む理由のいくつかのうちのひとつでしかありません。
私は一時期、「文字中毒」とでも言っていいか少し悩む状態になっていました。とにかくなにか読む。それは成分表でもなんでもいい。これは文字好きには時折ある症状だと思いますが、私がそうなった理由を、私は知っています。まったく違うジャンルの専門書、覚えていられる訳の無いもの。それらを読み進めるだけで楽しかった、あの楽しさの根っこの理由。
文字を読んでいる時間、私は世界に居なかった。私が望んだのは、その時間です。
物語の世界に入り込める、ではないのです。私は文字を読んでいるあの時間、現在も過去も未来も、全て文字で埋め尽くされた。私の内側が全て文字になる、あの時間を切望していた。この感覚は、おそらくどこかに同志がいるのではないかと思うくらい私には自然で、しかし近しい人に同じ人がいるとは思えない程度に仕舞い込んだものでした。
私はとにかく世界からいなくなる時間を好み、だからこそそれだけでよかったのです。私はそれが自分の糧になるなんて興味がありませんでした。だからこそ、意味がないことに意味があるという現在の価値観があるのかもしれません。私に欲しかったのは、そういう、自己の喪失、文字に体を奪われる時間でした。
だから、私は覚えていない物語がたくさんあります。タイトルを覚えているもの、表紙を見ればわかるもの、手に取って文字を追えば思い出すもの、それはさまざまです。さまざまな切れ端だけが残っていて、それは私が物語に生かされていた、いわゆる映画のチケットの半券、でした。
すぐに思い出さなくても、なにかあれば、ああ、こうだったと思える。忘れていても失っていないもの。私が物語に片思いをし続けた事実。テストの点数で愛を綴ってもその愛こそが文学を貶めるという、「私がしてはいけないこと」である自認が生んだ、最後のかけら。だからずっと、私は、物語がこちらを見ないと知りながら愛していたのです。
別にこれは純愛ではないでしょう。もっと醜悪で、自分勝手なもの。でも、昔と違って「何も悪くない」と今の私は知っています。こういう話ができるようになったのは最近で、だからこそ何度も掘り返しては、何度も「いいんだよ」と当時の私を許して、繰り返し繰り返し、許しても許しても足りない私に言い聞かせていました。私はずっと、許されたかった。それを私は、知っています。
物語は私を喪失させても、私を愛さない。それも私の理解のひとつでした。本を閉じれば、文字を追うのをやめれば、現在がすぐに私になる。私は私でいてしまう。文字を追わなくなると訪れるその当たり前の現実は、物語がこちらを向いていない理由でした。昔はなんでも読めたのに、読めるものが少しずつへっていったのもその為かもしれません。
物語、それもファンタジーの世界ではそれなりに「別れと記憶の喪失」はあります。物語を閉じてそれが糧になる。けれども覚えていない。それは物語からの拒絶の中でも一等苦しい所でした。私が覚えていれば違ったかもしれません。けれども私は、物語を覚えずに文字を食べていただけでした。それでいて、食べた事実に救われていたから厄介でした。
忘れる、が、思い出せるものなら別でしょう。でも、物語の中で登場人物が経験するのは完全な喪失です。忘却、失う。それは取り戻せず、物語を愛したことすら物語から拒否されるような心地でした。覚えていられない自分の不実を罪悪にするような瞬間でもありました。それでいて、物語はそういうものだと、知っていました。諦めていました。私が書かない限り、私は物語に拒絶され続けるのです。だから、恐怖であり罪悪でありしかし受け入れるしかないもの、だったのです。
そうして何度も繰り返したあきらめに、ジャックは、「忘れないよ」と言いました。彼はそもそも、メリーポピンズを見た時に見た目についても言及せず、喜び、そして彼女の相棒として子供たちの後ろを歩き、歌を歌い進んできた人でした。そんな彼が、忘れないよ、と言ったのです。
衝撃でした。でも多分、その時に相応しいのは衝撃と言う言葉でもなくて、まっしろに、その言葉だけが入り込んだような、そうして私はずっと泣いていました。
覚えていたい。忘れてしまうのは怖い。出会って、また、笑い合いたい。笑ったことの嬉しさの細かいことを忘れてしまうのは悲しい。 この感情は、私にとって身勝手でした。報われることがない、と思っていました。
でも、ジャックは、覚えてくれる。
このどうしようもない救いが、私にとってあの物語のジャックで、ただひたすら泣いてしまうものになりました。笑顔の彼が、私は好きです。
これまでの積み重ねが、彼がメリーポピンズを忘れず、覚えているということを信じさせてくれます。当たり前に本当だと、私はそれを慰めではなく素直に信じることが出来ました。別れの忘却ではなく、当たり前に続く世界があることを、信じることができたのです。
物語に片思いをずっとしていました。物語で出会う忘却を、覚えていられる人は選ばれた人で、それは証が必要なのだと思っていました。夢の世界の本当。でも私の半券は形が無くて、私は罪悪で。でも、私はあの映画でジャックを特別だと、思いませんでした。普通の優しい大人でした。
ジャックが持っている風船は特別でもなんでもなくて、みんなも持っていて。彼は特別メリーポピンズに繋がる物を持っていない。それでも「忘れない」と当たり前に言える。メリーポピンズは忘却されなくていいのだ。彼女の寂しさがなくなったことに安堵するよりも醜悪な自分勝手な感情で、私は救われて、泣き続けました。
きっと人には理解されない。それでもいい。考えず楽しむ映画は、私にとって許しで、自分だけでなく誰か他人に許されたかったのだと、そうして泣きながらまた私は私を抱きしめられるのだと、そのことが救いで仕方なかったのです。映画としては邪道な楽しみ方だろう、そう思いながら、私は本当に、出会ってよかった、と思いました。
なかったことにならない。忘却を強制されて終わらなくていい。その人がいたこと、かかわったこと、触れた時間。細かく残らなくてもいいんです。私は、それが、あったことを思うこと、そのものを許されたくて。
彼が覚えていられる。ただひたすらそれがやわらかい部分を包んでくれて、何度も何度も、泣いてしまう。
この映画を私は多分、シリーズとして見られる自信はありません。救いになりすぎて、他の要素を求められるかというとあまりに癒着したものが厄介だからです。でも私は、ジャックに救われた。この歳で彼のような大人でありたいではなく、彼のような大人に出会いたかったと願うのはあまりに幼稚だと思いながら、そんな気持ちを否定できずに泣きじゃくって、許しの言葉を繰り返しています。
この物語に出会えてよかった。出会う機会を頂けて本当によかった。ただただ感謝しかできず、私は許しを抱きしめ続けるのでしょう。
(鑑賞:2019/02/02 感想記事:2019/02/26 再掲:2023/01/16)

* * *
創作ネタ/蛇足一コマ感想